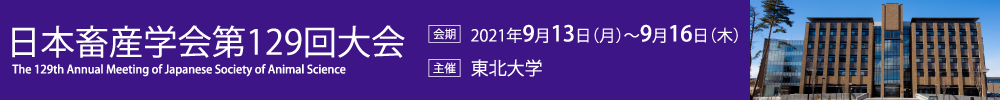[AW-05] 社会的ストレスモデルマウスによる巣作り遅延の行動評価システムの構築
動物の個体間に生じるストレス(社会的ストレス)は様々な健康リスクを増加させる。例えば、ヒトではうつ病発症のリスクを上げ、家畜では増体抑制や疾患リスクの増加などで生産性を低下させる。このように社会的ストレスは動物にとって深刻な影響をもたらすにも関わらず、社会的ストレスによる行動生理への影響を詳細に理解できているとは言えない。そこでマウスを実験モデルとして用いて、マウスの個体間におこる社会的ストレスが行動生理にどう影響するのかに着目して研究した。その結果、社会的ストレスが巣作り行動に影響することを発見し、以下の一連の成果を得た。
1. 慢性的な社会的ストレス暴露と巣作りへの影響
巣作り行動は生得的行動であり、敵からの防御、温度調節、睡眠、養育など、生物が生存する上で大変重要な役割を果たす。この行動は目標指向性の行動であり、様々なモデルマウスにおいてモチベーションの評価に使用されている。本モデルは社会的ストレスを想定して、ストレスを与える側であるICRマウスのテリトリーにストレスを受ける側のC57BL/6J(B6)マウスを侵入させ、侵入したB6マウスはICRマウスから強い排他的攻撃をうけた。その後、B6マウスは透明な穴の空いた仕切りを隔てた隣の区画に移され、24時間同ケージ飼育された。10日間にわたるこのような排他的行動を受けた結果、B6マウスの心理的ストレスが慢性化し、巣作り行動が著しく遅延することを定量的に明らかにした (日本畜産学会第120回大会、2015年; Otabi et al., Behav. Processes., 2016)。本来備わっているはずの巣作り行動が障害されているこの状況は、意欲の低下を意味すると考えられ、巣作り行動が社会的ストレスによるヒト・動物のこころへの影響を反映しうる強力なモデルであることが強く示唆された。
2. 簡易的な向精神薬スクリーニング方法の開発とその妥当性
5分間の単発の社会的ストレスでも10日間の慢性社会的ストレスと同様に、巣作りが遅延することが判明した。そこで単発の社会的ストレスと巣作り遅延現象を組み合わせたパラダイムを確立し、巣作り障害の発見から向精神薬スクリーニング方法の開発に発展させた。その結果、巣作り行動の失調を起こすダウン症モデルマウスの巣作りを改善することが知られている5HT2a受容体拮抗薬を腹腔内投与すると、巣作り障害が一部レスキューされることを見出した(Otabi et al., Behav. Processes., 2017)。
3. 3次元深度センサを用いた急性社会的ストレスモデルにおける行動解析
社会的ストレスモデルマウスは特に明期の間に巣作りの開始を著しく妨げ、暗期後に巣作りが完了していたことから、暗期に巣作り意欲を回復させている可能性があった。しかしそのメカニズムは不明であった。このモデルマウスの巣作り意欲が回復するメカニズムを解明するための第一歩として、ストレスを受けた後の巣作りの全過程を観察することにした。暗期にホームケージ内の巣を目視で客観的に評価することは困難であるため、3次元カメラを利用し単発の社会的ストレスによって誘発される行動障害を岡山ら(J. Neurosci. Methods., 2015)の3次元解析システムを発展させ、3次元データを取得した(日本畜産学会第120回大会、2015年; Otabi et al., Anim. Sci. J., 2020)。その結果、モデルマウスでは、自発活動量の増加、探索行動であるリアリング(立ち上がり)行動の減少および巣作りの遅れが見られたが、暗期には巣作り行動は徐々に回復した。さらに、モデルマウスでは巣作り行動とストレスを与えたマウスを避ける社会的忌避行動の間に正の相関傾向が見られた。このようなことからモデルマウスが巣材を提供されてすぐに巣作りに着手しない原因が、単純な自発活動の低下ではないことが分かった。このシステムは詳細な動物の行動データを取得することができるため、3次元システムによる行動評価は家畜や家禽の飼育管理にも応用が可能だと考える。
【略歴】 茨城大学農学部生物生産科学科卒。同大学大学院同研究科修士課程同専攻修了。日本学術振興会特別研究員DCに採用。東京農工大学大学院連合農学研究科博士課程生物生産科学専攻にて博士号(農学)取得。現在、摂南大学農学部にて特任助教およびAMED 医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE)の「医療用ブタ製造を目指した基盤整備」プロジェクト研究員に就任。
1. 慢性的な社会的ストレス暴露と巣作りへの影響
巣作り行動は生得的行動であり、敵からの防御、温度調節、睡眠、養育など、生物が生存する上で大変重要な役割を果たす。この行動は目標指向性の行動であり、様々なモデルマウスにおいてモチベーションの評価に使用されている。本モデルは社会的ストレスを想定して、ストレスを与える側であるICRマウスのテリトリーにストレスを受ける側のC57BL/6J(B6)マウスを侵入させ、侵入したB6マウスはICRマウスから強い排他的攻撃をうけた。その後、B6マウスは透明な穴の空いた仕切りを隔てた隣の区画に移され、24時間同ケージ飼育された。10日間にわたるこのような排他的行動を受けた結果、B6マウスの心理的ストレスが慢性化し、巣作り行動が著しく遅延することを定量的に明らかにした (日本畜産学会第120回大会、2015年; Otabi et al., Behav. Processes., 2016)。本来備わっているはずの巣作り行動が障害されているこの状況は、意欲の低下を意味すると考えられ、巣作り行動が社会的ストレスによるヒト・動物のこころへの影響を反映しうる強力なモデルであることが強く示唆された。
2. 簡易的な向精神薬スクリーニング方法の開発とその妥当性
5分間の単発の社会的ストレスでも10日間の慢性社会的ストレスと同様に、巣作りが遅延することが判明した。そこで単発の社会的ストレスと巣作り遅延現象を組み合わせたパラダイムを確立し、巣作り障害の発見から向精神薬スクリーニング方法の開発に発展させた。その結果、巣作り行動の失調を起こすダウン症モデルマウスの巣作りを改善することが知られている5HT2a受容体拮抗薬を腹腔内投与すると、巣作り障害が一部レスキューされることを見出した(Otabi et al., Behav. Processes., 2017)。
3. 3次元深度センサを用いた急性社会的ストレスモデルにおける行動解析
社会的ストレスモデルマウスは特に明期の間に巣作りの開始を著しく妨げ、暗期後に巣作りが完了していたことから、暗期に巣作り意欲を回復させている可能性があった。しかしそのメカニズムは不明であった。このモデルマウスの巣作り意欲が回復するメカニズムを解明するための第一歩として、ストレスを受けた後の巣作りの全過程を観察することにした。暗期にホームケージ内の巣を目視で客観的に評価することは困難であるため、3次元カメラを利用し単発の社会的ストレスによって誘発される行動障害を岡山ら(J. Neurosci. Methods., 2015)の3次元解析システムを発展させ、3次元データを取得した(日本畜産学会第120回大会、2015年; Otabi et al., Anim. Sci. J., 2020)。その結果、モデルマウスでは、自発活動量の増加、探索行動であるリアリング(立ち上がり)行動の減少および巣作りの遅れが見られたが、暗期には巣作り行動は徐々に回復した。さらに、モデルマウスでは巣作り行動とストレスを与えたマウスを避ける社会的忌避行動の間に正の相関傾向が見られた。このようなことからモデルマウスが巣材を提供されてすぐに巣作りに着手しない原因が、単純な自発活動の低下ではないことが分かった。このシステムは詳細な動物の行動データを取得することができるため、3次元システムによる行動評価は家畜や家禽の飼育管理にも応用が可能だと考える。
【略歴】 茨城大学農学部生物生産科学科卒。同大学大学院同研究科修士課程同専攻修了。日本学術振興会特別研究員DCに採用。東京農工大学大学院連合農学研究科博士課程生物生産科学専攻にて博士号(農学)取得。現在、摂南大学農学部にて特任助教およびAMED 医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE)の「医療用ブタ製造を目指した基盤整備」プロジェクト研究員に就任。